 今回の発掘で、邪馬台国・大和説派は大和に決着したと勢いづいています。たしかに、地味な発掘作業は、大和の方が熱心なようです。最近は、九州説に加担するような発掘がないように思います。考古学に関しては、大和は活発です。
今回の発掘で、邪馬台国・大和説派は大和に決着したと勢いづいています。たしかに、地味な発掘作業は、大和の方が熱心なようです。最近は、九州説に加担するような発掘がないように思います。考古学に関しては、大和は活発です。しかし、この発掘について、寺澤黛・奈良県立橿原考古学研究所総務企画部長は「卑弥呼の治世は女王国に与しない国々も少なくなかった。不安定な時代に、箸墓のような隔絶した大型古墳が築かれたとは考えにくい」として、箸墓は卑弥呼の墓とは認めていません。箸墓が、卑弥呼の墓としますと、いきなり前方後円墳が現れたことになり、矛盾を感じます。また、魏志倭人伝にも卑弥呼の墓は、周囲が百歩の円墳と書いています。やはり合いません。墓は、円墳に始まり、方墳、ホタテ貝型から前方後円墳に進化して行ったと考えるのが、常識でしょう。
 邪馬台国・大和説の学者は、纒向遺跡から「親魏倭王」の金印が出て来ることを願っています。しかし、これが発掘されても、北九州から東征した折に持って来たということになりかねませんので、依然として結着は着きません。福岡からは、唯一の「漢倭奴国王」の金印が出土しています。仮に博多が奴国としますと、邪馬台国が大和では、あまりに遠いように思います。また、ここが卑弥呼の邪馬台国であったならば、大和朝廷に引き継がれたことでしょう。三種の神器よりももっと重要なものであったはずです。
邪馬台国・大和説の学者は、纒向遺跡から「親魏倭王」の金印が出て来ることを願っています。しかし、これが発掘されても、北九州から東征した折に持って来たということになりかねませんので、依然として結着は着きません。福岡からは、唯一の「漢倭奴国王」の金印が出土しています。仮に博多が奴国としますと、邪馬台国が大和では、あまりに遠いように思います。また、ここが卑弥呼の邪馬台国であったならば、大和朝廷に引き継がれたことでしょう。三種の神器よりももっと重要なものであったはずです。わたしは、やはり邪馬台国は、北九州にあり、東征して、大和朝廷になったと思います。これであれば、日本書紀の記述とも合います。しかし、こういうことは、いたずらに結論を急がない方が、古代ファンにとっては、楽しみがあります。
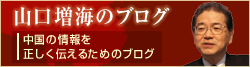








0 件のコメント:
コメントを投稿