 10月29日の弥生時代の農耕遺跡の御所市玉手遺跡をブログに書きましたが、ここに近い秋津地区で、葛城氏の祭祀跡と思われる遺構が見つかりました。今、この地区は京奈和自動車道の建設中で、その事前調査で見つかったものです。この遺跡は、4世紀前半と推定されております。ここから、木製の分厚い塀が出土しています。この塀の中に掘っ立て柱建築物が4棟あったと見られ、その建物を囲むように木製の塀で囲まれていました。これは、大阪府八尾市の心合寺山古墳の「囲型埴輪」の囲いの構造と一致しています。
10月29日の弥生時代の農耕遺跡の御所市玉手遺跡をブログに書きましたが、ここに近い秋津地区で、葛城氏の祭祀跡と思われる遺構が見つかりました。今、この地区は京奈和自動車道の建設中で、その事前調査で見つかったものです。この遺跡は、4世紀前半と推定されております。ここから、木製の分厚い塀が出土しています。この塀の中に掘っ立て柱建築物が4棟あったと見られ、その建物を囲むように木製の塀で囲まれていました。これは、大阪府八尾市の心合寺山古墳の「囲型埴輪」の囲いの構造と一致しています。丸木を板にするのは、当時は、鋸がありませんから、槍鉋で削っていかねばなりませんから、平たい板を作るのは、大変です。槍鉋は、玉手遺跡にもありました。今、使われている鉋は、台鉋といって、室町時代から使われ始めたものです。
この秋津地域は、葛城氏の勢力範囲と思われ、葛城山の頂上にいた神様を塀の中に呼んで、秘儀を執り行ったのではといわれています。葛城襲津彦の娘・磐之媛は仁徳天皇の皇后で履中、反正、允恭の3代の天皇の母です。
 大阪・河内地方の王権を支え、絶大な権力を誇ったようです。
大阪・河内地方の王権を支え、絶大な権力を誇ったようです。この大和盆地の南部には、4世紀前半に、東の巻向、西の葛城といった二大勢力が拮抗していたものと思われます。大和盆地の東の巻向を勢力範囲とする勢力は、三輪山をご神体とし、西を勢力範囲とする勢力は、葛城山をご神体としていました。そして、この葛城勢力は、帰化勢力をバックにした蘇我氏に吸収されていきます。大和朝廷草創期の話です。
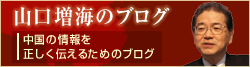








1 件のコメント:
11月28日秋津遺跡の現地説明会に行ってきました。
発掘担当の橿考研もこの遺跡についてまったく理解していない。
私なりに推測するこの遺跡の性格があります。
よろしかったらアクセスしてみてください。
邪馬台国出現のキーワードでヒットすると思います。
http://yamatai.sblo.jp/?1291376616
コメントを投稿