 先に茶臼山古墳を見たときの感想を書きましたが、その後の地道な調査で、81面の鏡の破片が見つかりました。昭和24、25年の調査で22面、今回が59面で、合わせて81面というわけです。これまでは、福岡県前原市平原1号墓の40面が最多でしたが、これを大幅に更新しました。平原1号墓は弥生時代のものであり、古墳時代のものでは、京都府木津川市の椿井大塚山古墳の37面、奈良県天理市の黒塚古墳の34面が、多く発見されたものでしたが、それらの倍以上で、型も13種と最多でした。しかし、完全なものはなく、すべて破片というのも謎です。
先に茶臼山古墳を見たときの感想を書きましたが、その後の地道な調査で、81面の鏡の破片が見つかりました。昭和24、25年の調査で22面、今回が59面で、合わせて81面というわけです。これまでは、福岡県前原市平原1号墓の40面が最多でしたが、これを大幅に更新しました。平原1号墓は弥生時代のものであり、古墳時代のものでは、京都府木津川市の椿井大塚山古墳の37面、奈良県天理市の黒塚古墳の34面が、多く発見されたものでしたが、それらの倍以上で、型も13種と最多でした。しかし、完全なものはなく、すべて破片というのも謎です。銅鏡の内訳は、
三角縁神獣鏡 26面、
内行花文鏡(国産)10面
同 (輸入)9面
画文帯神獣鏡、斜縁神獣鏡、四乳神獣鏡 16面
半肉彫獣帯鏡 5面
環状乳神獣鏡 4面
だ龍鏡 4面
細線獣帯鏡 3面
方格規矩鏡 2面
単き鏡 1面
盤龍鏡 1面
魏志倭人伝には「中国皇帝が卑弥呼に『太刀や銅鏡などを汝の国中の人に示せ』と伝えた」と記されています。
今回、見つかった「正始元年」鏡の破片は、1.5センチ大で、群馬県高崎市の蟹沢古墳など3古墳で見つかっている「正始元年」の年号入りの鏡と同じ鋳型であることも確定しました。これらの銅鏡には、繊維あとがあり、銅鏡を1枚1枚、絹の布に包んで葬ったようです。この「正始元年」は、西暦240年にあたります。倭国の女王・卑弥呼が中国の魏に派遣した使節が帰国した年です。
この茶臼山古墳は、誰が葬ってあるのでしょうか。茶臼山古墳の築造は、3世紀末から4世紀初めと比定されていますので、崇神天皇、景行天皇の三輪王朝の前の王朝と思います。となると、やはり卑弥呼か臺与ということになります。そうなると、邪馬台国は大和ということになります。わたしは、神武東征を信じたいので、まだ結論は出ない方が、いろいろ想像できて楽しいです。最近の発掘は、邪馬台国近畿説を補強するものばかりで、北部九州の考古学者の活躍をのぞみたいものです。
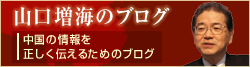








0 件のコメント:
コメントを投稿