 幕末から明治維新にかけて、宇和島藩は注目を浴びて来ます。藩主伊達宗城が、薩摩の島津斉彬、福井の松平春嶽、土佐の山内容堂らとともに幕末の四賢人といわれているほどにオピニオン・リーダー的なところもあったからでしょう。この四藩の中では、宇和島は小藩です。それでは、この時代に宇和島藩は、どのような立場にあったのでしょうか。十万石というのは決して大藩ではなく、しかも外様大名です。宇和島は、四国でも江戸から見ますとかなり僻地という印象があるのですが、宇和島は四国の中でも西の僻地ともいえます。ところが、幕末に幕府に対して非常な影響力を持ったのは、薩摩、長州、越前、そしてこの宇和島藩です。特に伊達宗城という藩主は、その当時の世論の指導者的役割を果たしました。
幕末から明治維新にかけて、宇和島藩は注目を浴びて来ます。藩主伊達宗城が、薩摩の島津斉彬、福井の松平春嶽、土佐の山内容堂らとともに幕末の四賢人といわれているほどにオピニオン・リーダー的なところもあったからでしょう。この四藩の中では、宇和島は小藩です。それでは、この時代に宇和島藩は、どのような立場にあったのでしょうか。十万石というのは決して大藩ではなく、しかも外様大名です。宇和島は、四国でも江戸から見ますとかなり僻地という印象があるのですが、宇和島は四国の中でも西の僻地ともいえます。ところが、幕末に幕府に対して非常な影響力を持ったのは、薩摩、長州、越前、そしてこの宇和島藩です。特に伊達宗城という藩主は、その当時の世論の指導者的役割を果たしました。吉村昭氏も次のように書いています。
「なぜ、このような藩が、さまざまな悪条件を持っていながら、世論の指導的立場に立つことができたのかということを考えて見ますと、いろいろあると思うのです。
第一に、やはり大きな発言力を持つという背景には、どんな場合でもそうですけれども、経済力がなければならない。最初は徹底した倹約政策です。当時の記録を見ますと、どんな人間でも木綿かさらし以外の着物を着てはいけない、絹物なんかとんでもない。いろいろな細かいことが書いてありまして、かまぼこも色をつけたものを売ってはいけない。同時に経済力を強めるためには、経済学者の佐藤信淵を重んじまして、藩士の小池九蔵を佐藤の門に入れるなど、非常に進歩的な経済政策をとりました。
第二は、人の和といいますか、宇和島藩の藩論が見事に統一されていた。藩論をひきいる最高の人物は伊達宗城。宗城は、はじめかなり徹底した攘夷論者であった。それが、天皇を議長とした、幕府をそのまま維持する協議会みたいなもので国の政治をやって行こう、という考え方に変わっていきます。それから最後は、開国、大政奉還と、目まぐるしい変わりかたをしています。
藩士たちが、反発するようなことがなく、宗城の意見のままに従う。そういう藩論の統一が見事になされ、人の和によって宇和島藩が強化された。これによって、小藩といえど力をもったということのようです。
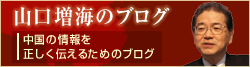




0 件のコメント:
コメントを投稿