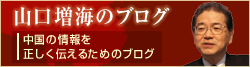後藤氏は、「老化という言葉は、何歳ぐらいから意識されはじめるのでしょうか。若いころには他人事のように感じられた老化という現象が、歳を重ねるにつれ、事あるごとに意識にあがってくるといった具合でしょうか。
あるいは、周りの同年代の衰えぶりを目の当たりにするたびに、いつしか老化という現象を受け入れざるをえなくなるのでしょうか」と問うています。老化を押しとどめることはできるはずもないと誰もが思っていますが、権力を握ったひと、莫大な富を築いたひとが、お金で、あるいは権力で自分だけは老化は受け入れず、死さえも受け入れることが出来ずにさまざまな方法を試みてきました。
有名なのは、秦の時代に始皇帝の命を受けて莫大な費用をかけて東海に乗りだした徐福の一団があります。徐福は、現在のいちき串木野市に上陸し、同市内にある冠嶽に自分の冠を奉納したことが、冠嶽神社の起源と言われます。冠嶽神社の末社に、蘇我馬子が建立したと言われるたばこ神社(大岩戸神社)があり、天然の葉たばこが自生しているそうです。徐福が上陸したと伝わる三重県熊野市波田須から2200年前の中国の硬貨である半両銭が発見されています。波田須駅1.5kmのところに徐福ノ宮があり、徐福が持参したと伝わるすり鉢をご神体としています。
どうやら、徐福が日本に来た確率は高いようですが、徐福は不老不死に効く薬草は発見できずにそのまま日本に埋もれたようです。
そのほか、多くの人が不老不死の霊薬や護符を求めましたが、それを実現したという話は古来、聞こえたためしがありません。しかし、現代になって、老化研究(老科学)とアンチエイジング(抗加齢)医学研究の最前線から、これまでの常識を覆すような新しい知見が出てきました。その知見を一言でいえば、「老化は病気であり、病気である以上、治療の対象となる」というものです。研究の成り行きによっては、かつて錬金術師たちが夢見た不老さえも実現できるのではないか―そんな可能性が見えてきたのです。