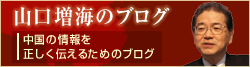これに対し、アップル社のクック最高経営責任者(CEO)は、グループ内の配当という形での資金供与は米国の法律では課税対象ではなく、すべて合法的な税務処理であると反論していることは、テレビなどでも報道されているとおりです。
今のところ、アップル社だけが標的にされていますが、同業のマイクロソフト社やヒューレット・パッカード社も米上院のヒアリングに呼ばれるかもしれないと言われています。英国では、スターバックス社がやはり国際課税で問題になっていますが、日本のスターバックス社は、ちゃんと税金を払っているそうです。
欧米各国ともに大規模な租税回避に対して、厳しい見方をしてきています。
米国の法人税率は35%、実質税率でも30.5%です。このため、各国の税制の違いを利用して節税せざるをえないというわけです。理論的には、個人段階で、すべて課税できれば法人税は不要ですが、実際には個人段階の課税は不可能なので法人税があるわけです。
いずれ国際協調などによって各国の法人税率は一定の範囲内に収束していくだろうと高橋洋一氏は述べています。この問題は、当分は火種が消えるどころかもっと大きくなるでしょう。