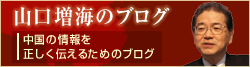中国が景気の過熱を防止するために9月15日、1年物の貸出基準金利を0.27%引き下げて7.20%としました。日本とは、大違いです。中国は、土地への投資を抑制しています。先日、上海の物件を見に行きましたが、建物を建てて売るということでした。なぜ?と聞きますと、詳しくは言いませんでしたが、不動産のみの販売では、銀行の貸出が得られないために建物を作って売るということでしょう。また、大手銀行を除く中小金融機関の預金準備率を1%、四川大地震被災地の金融機関の預金準備率を2%それぞれ引き下げました。
中国が景気の過熱を防止するために9月15日、1年物の貸出基準金利を0.27%引き下げて7.20%としました。日本とは、大違いです。中国は、土地への投資を抑制しています。先日、上海の物件を見に行きましたが、建物を建てて売るということでした。なぜ?と聞きますと、詳しくは言いませんでしたが、不動産のみの販売では、銀行の貸出が得られないために建物を作って売るということでしょう。また、大手銀行を除く中小金融機関の預金準備率を1%、四川大地震被災地の金融機関の預金準備率を2%それぞれ引き下げました。
利下げは2002年2月以来6年7ヵ月ぶりです。預金準備率の引き下げは1999年11月以来の8年10ヵ月ぶりです。
中国の国内総生産(GDP)の伸び率は、今年上半期が10.4%と昨年後半からの減速傾向が顕著になって来たための対策です。特に輸出が人民元の急上昇や原材料の高騰で減速しました。このため、政府は、景気過熱防止から安定にして比較的速い成長に軌道修正を行いました。
8月からは、繊維製品の輸出に対して、実質上の減税に踏み切るとともに貸出限度枠を拡大し、資金に苦しむ企業を援助しています。
中国政府は、現在黒字であり、いろいろの手が打てます。着実な手の打ち方に感心します。過去に日本は、プラザ合意で急激な円高を押しつけられました。しかし、中国首脳は、このような圧迫には屈せず、緩やかな人民元高を選択しています。日本と中国の自主性の差は何でしょう。島国根性と中華思想の差でしょうか。中国と日本は、近くにこのような参考になる国があります。もっと切磋琢磨して、国ではなく、国民を豊かにして欲しいものです。
 汚染米問題で、やっと太田誠一農水大臣、白須敏朗次官が同時に辞任しました。困ったものです。農水大臣の職は、この2年間で5人が代わり、今回で6人目になります。5人の中では、この太田大臣が一番に長かったくらいです。松岡利勝(18年9月26日~19年5月28日)、赤城徳彦(19年6月1日~19年8月1日)、遠藤武彦(19年8月27日~19年9月3日)、若林正俊(19年9月4日~20年8月1日)、太田誠一(20年8月2日~20年9月19日)。大臣と次官が同時に辞任することは、異例です。
汚染米問題で、やっと太田誠一農水大臣、白須敏朗次官が同時に辞任しました。困ったものです。農水大臣の職は、この2年間で5人が代わり、今回で6人目になります。5人の中では、この太田大臣が一番に長かったくらいです。松岡利勝(18年9月26日~19年5月28日)、赤城徳彦(19年6月1日~19年8月1日)、遠藤武彦(19年8月27日~19年9月3日)、若林正俊(19年9月4日~20年8月1日)、太田誠一(20年8月2日~20年9月19日)。大臣と次官が同時に辞任することは、異例です。
太田氏は、早稲田大学の学生を中心とするアソビ系サークル「スーパーフリー」に参加していた女子大生が集団で暴行されていた事件で、「集団レイプする人は元気があるからいい。正常に近いじゃないか」というような発言をして、大きく非難されました。このときは、海外のBBCやCBSなどにも取り上げられ、この発言が大きく影響し、2003年の第43回衆議院議員総選挙では落選しています。福岡の選挙民は、正常に反応しました。
最近では、福田康夫改造内閣農林水産大臣就任直後の2008年8月10日、NHKの番組「日曜討論」に出演した際、食の安全対策について問われ、「日本国内は心配ないと思っているが、消費者がやかましいから徹底する」と発言しました。このときは、麻生太郎氏などが、助け舟を出して、辞任には至りませんでした。
今回も9月12日のテレビ番組で「人体に影響がないことは自信を持って申し上げられる。だから、あんまりじたばた騒いでいない」と発言し、さすがの福田首相の怒りを買いました。農水省には任せられないと、野田聖子消費者行政担当大臣に主導権を与えました。
 白須氏は11日の記者会見で「一義的には(不正を行った)企業の責任で、私どもに責任があると今の段階では考えているわけではない」と発言しました。さすがの福田首相も「5年間に96回も立ち入り検査をしていながら、一度も発見できない検査というのは一体何なんだ」と白須氏の『役所の論理』に怒り心頭に達しました。
白須氏は11日の記者会見で「一義的には(不正を行った)企業の責任で、私どもに責任があると今の段階では考えているわけではない」と発言しました。さすがの福田首相も「5年間に96回も立ち入り検査をしていながら、一度も発見できない検査というのは一体何なんだ」と白須氏の『役所の論理』に怒り心頭に達しました。
農水省の役人は、どんな仕事をしているのでしょう。農水省、地方農政局、農政事務所と階層を重ね、かえって見えにくくなっているのでしょう。農水省に限らず、中央官庁には平成維新が必要なようです。誰が、大ナタを振るってくれるのでしょう。
 中国が景気の過熱を防止するために9月15日、1年物の貸出基準金利を0.27%引き下げて7.20%としました。日本とは、大違いです。中国は、土地への投資を抑制しています。先日、上海の物件を見に行きましたが、建物を建てて売るということでした。なぜ?と聞きますと、詳しくは言いませんでしたが、不動産のみの販売では、銀行の貸出が得られないために建物を作って売るということでしょう。また、大手銀行を除く中小金融機関の預金準備率を1%、四川大地震被災地の金融機関の預金準備率を2%それぞれ引き下げました。
中国が景気の過熱を防止するために9月15日、1年物の貸出基準金利を0.27%引き下げて7.20%としました。日本とは、大違いです。中国は、土地への投資を抑制しています。先日、上海の物件を見に行きましたが、建物を建てて売るということでした。なぜ?と聞きますと、詳しくは言いませんでしたが、不動産のみの販売では、銀行の貸出が得られないために建物を作って売るということでしょう。また、大手銀行を除く中小金融機関の預金準備率を1%、四川大地震被災地の金融機関の預金準備率を2%それぞれ引き下げました。