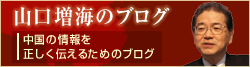.jpg) 9月8日、海上保安庁が公務執行妨害容疑で、中国漁船の船長・詹其雄(41)を逮捕しました。10日には、中国の楊潔篪外交部部長が丹羽宇一郎中国大使を呼びだし抗議しました。さらに12日にも戴秉国国務委員(副首相級)が丹羽大使を呼び出して抗議しました。13日には、全人代の李建国常務委員会副委員長の訪日延期を通告して来ました。険呑な空気の中、19日に船長の拘留期限を10日間延長しました。途端に中国側から反撃に出られ、閣僚級以上の交流停止を表明され、王光亜外交部副部長が丹羽大使に電話で抗議しました。20日には、中国招待の1000人の日本人の訪中計画が延期になりました。21日には、温家宝首相が「即時無条件釈放」を要求しました。23日には、エアアースの対日輸出の禁止が報道されました。さらにフジタの社員4名が、石家荘で軍事施設を撮影していたとして逮捕されました。この状況に24日、那覇地検次席検事が釈放の声明を行いました。フジタの社員のうち、3名は釈放されました。今回の事件の流れです。
9月8日、海上保安庁が公務執行妨害容疑で、中国漁船の船長・詹其雄(41)を逮捕しました。10日には、中国の楊潔篪外交部部長が丹羽宇一郎中国大使を呼びだし抗議しました。さらに12日にも戴秉国国務委員(副首相級)が丹羽大使を呼び出して抗議しました。13日には、全人代の李建国常務委員会副委員長の訪日延期を通告して来ました。険呑な空気の中、19日に船長の拘留期限を10日間延長しました。途端に中国側から反撃に出られ、閣僚級以上の交流停止を表明され、王光亜外交部副部長が丹羽大使に電話で抗議しました。20日には、中国招待の1000人の日本人の訪中計画が延期になりました。21日には、温家宝首相が「即時無条件釈放」を要求しました。23日には、エアアースの対日輸出の禁止が報道されました。さらにフジタの社員4名が、石家荘で軍事施設を撮影していたとして逮捕されました。この状況に24日、那覇地検次席検事が釈放の声明を行いました。フジタの社員のうち、3名は釈放されました。今回の事件の流れです。船長の逮捕を強硬に主張したのが、海保を所管する前原誠司国土交通相(当時)でした。岡田外務大臣(当時)も前原氏と同様に強硬姿勢だったようです。珍しく仙谷官房長官は、穏便な措置を図ろうとしたようですが、この二人に説きふせられて、船長の逮捕に踏み切りました。
これを受けて菅首相は、「わが国の法律に基づいて厳正に対応していく」と語り。8日夜にも、「法律に基づく対応」と2度繰り返しました。仙谷長官も「厳正に対応していく」「ガス田にも影響せず」と強硬姿勢を繰り返しました。
しかし、誤算は程なく生じました。送検された船長は否認を続けました。容疑者が否認する場合、通常、逮捕後の拘置は避けられません。事件は長期化しました。拘置延長で、起訴は確実との見方は広がっていました。中国政府は、次々に対抗処置を実行しました。王光亜外交部副部長は、「船長を無条件に既時釈放しなければ、強烈な対抗措置を取る」と警告しました。
訪米中の温家宝首相は、21日、船長の既時無条件の釈放を公然を求め始めますと、同日からレアアース(希土類)の対日輸出が止まりました。そして河北省でフジタの日本人社員4人が拘束されたと官邸に伝わると強硬論はとどめを刺されました。
23日のニューヨークでの日米首脳会談の直後、船長の釈放に向けた動きが一気に表面化しました。首相は渡米する直前、「何とかしろ」と仙谷長官に伝え、国会召集前にこの問題の幕引きを図るよう指示していました。
船長逮捕後のシナリオのない情けなさ
前原氏は、八ケ場ダムでも、大見得を切って、ダム建設中止を指示しましたが、止まることなく進んでいます。ハッタリは得意ですが、あとに何にもありません。思い出すのは、偽メール事件です。永田議員が怪しい人物から受け取った偽メールで「明日の国会を期待してください」と、マスコミほかを引きつけましたが、偽メールであることが分かりました。こういったパフォーマンスは前原氏の得意技ですが、松下政経塾で鍛えられたものかも分かりません。永田議員は、辞職し、北九州市の病院で投身自殺をしました。どうも前原氏は、危なっかしい人物です。首相が菅氏、官房長官が仙谷氏、幹事長が岡田氏という組み合わせも気になります。(明日に続く)