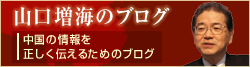|
| 政庁跡から北側の少し離れたところにある歌碑 |
ところが、大伴郎女が間もなく亡くなってしまいました。追い打ちをかけるように、弟の訃報まで届きました。
《世の中は 空しきものと知る時し いよよますます かなしかりけり》
6月23日のことでした。
奈良の都では、新興氏族の藤原氏が台頭していました。頼みとする左大臣・長屋王も天平元(729)年2月、藤原氏の讒言によって自死してしまいました(長屋王の変)。軍人氏族として、旅人は焦りましたが、遠い九州にいては、何もできません。
この憂さをはらすべく、筑前国守として赴任中の山上憶良らと交流し、数々の秀歌が生み出しました。
ようやく平城京に戻れたのは、天平2(730)年暮れでした。都では、自分より年少の藤原武智麻呂ら4兄弟が、朝廷を牛耳る時代となっていました。厄介な軍人氏族の大伴旅人をはるか遠くに追いやったのちに藤原氏は、これも厄介な長屋王を自殺させました。天網恢恢疎にして漏らさず、藤原四兄弟は天然痘によって地獄に墜ちました。
旅人は翌年67歳で亡くなりました。
わたしは、旅人といい、家持といい、好きな万葉歌人です。